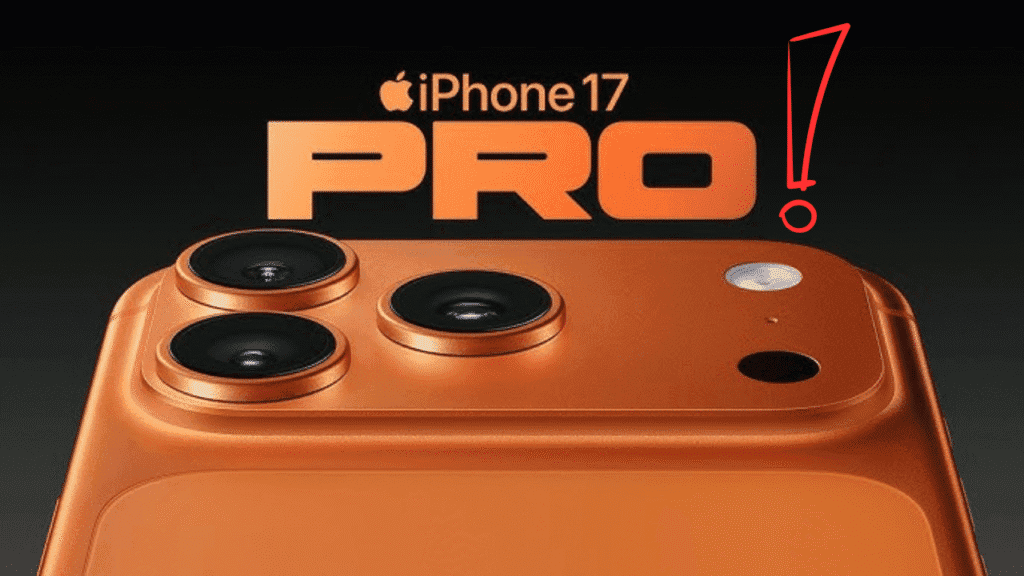メタ説明: 「それスノ」とは何か? この一見単純なフレーズが、天気予報の領域を超え、SNS、ビジネス、アート、そして現代の日本的共感の象徴となった軌跡を、最新の動向を含めて詳しく探ります。
はじめに:デジタル時代のささやかな驚き
ある冬の朝、あなたはカーテンを開ける。外を見ると、いつもと景色が違う。夜のうちに静かに、しかし確かに、白い結晶が街を覆っている。思わず口をついて出る言葉。「あ、雪が積もってる」。
この誰もが経験したことのあるささやかな驚きと感動の瞬間。この個人の内面で起こる感情の動きが、いま、インターネットという公共の空間で共有され、一種の文化的記号として昇華されているのをご存知だろうか。その中心にあるのが、たった三文字のキーワード「それスノ」なのである。
本稿では、「それスノ」という現象を多角的に解剖する。その起源から、SNSにおける爆発的広がり、メディアや企業による取り上げられ方、言語学的な特徴、そして最新の応用や派生現象に至るまで、この小さなフレーズが持つ大きな文化的価値に迫る。

第1章: 「それスノ」の起源と定義 ― それはどこから来たのか?
「それスノ」は、英語に直訳すれば「That snow」となる、文法的には不完全とも取れるフレーズである。しかし、その本質は完全な文章にあるのではなく、瞬間的に切り取られた感情の断片にある。
その直接の起源は、Twitter(現:X) を中心としたソーシャルメディアにあるとされる。正確な発信源や最初のツイートはインターネットの海に埋もれて特定困難だが、2010年代後半から特に見られるようになった。当初は、文字通り「雪が降っている/積もっている」という事実を報告する、ごく普通のツイートとして使われ始めた。
しかし、その表現が持つ独特の「間」と「省略」が、日本のネットユーザー、特に若年層の感性に刺さった。完全な文章で「雪が降っています」と報告するよりも、「それスノ」という一言で済ませる軽さ、即時性、そしてある種のクールさが支持されたのである。
「それスノ」の核心的な定義は以下のようになる:
眼前の雪景色という事象を発見し、それを他者と共有したいという衝動から発せられる、短く、即時的で、共感を誘う表現。 多くの場合、写真や動画を伴い、文章自体は極限まで省略されている。
これは、より長い表現である「雪が降ってる…!」や「積もってる!」の現代的な省略形と言える。そして、この「省略」こそが、この現象を理解する最大の鍵なのである。
第2章: なぜ「それスノ」は共感を呼ぶのか? ― 言語学と社会心理学からの考察
「それスノ」が単なる天気報告で終わらず、一種の文化コードとなった背景には、深い言語学的および心理学的な理由が存在する。
1. 言語の省略と「間」の力
日本語は本来、文脈に依存する高度な省略言語である。「それ(が)スノ(だ)」という構造は、主語と述語を最低限の形でつなぎ、あとは全てを読み手の想像力に委ねる。この「省略」によって、むしろ豊かなイメージが喚起される。発信者は、雪という事実を提示するのみで、感動や驚きの感情は直接言葉にしない。読み手は、その空白(間)を自身の経験や感情で埋めることで、より能動的かつ深く共感するのである。これは、俳句の「切れ」や、現代の若者言葉に見られる「空気を読む」文化と通底する。
2. 非日常の共有と「贈与」としての価値
雪は、特に都市部では非日常的な光景である。それは日常のルーティンを一時停止させ、人々に小さなワンダー(驚嘆)を与える。その非日常的な瞬間を、個人がスマートフォンで写真に収め、即座にSNSにアップロードして共有する行為は、デジタル時代におけるささやかな「贈り物」 と言える。
発信者は「この美しい/珍しい光景を、見逃しているかもしれないあなたにも見せてあげたい」という無償の贈与の精神で投稿する。受け取った側は、「いいね!」や「わかる!」という反応でそれに応える。この小さな贈与と応答の連鎖が、SNS上に弱いつながりながらもポジティブな共感コミュニティを形成する。
3. 低コンテクストなのに高共感
一般的に、省略の多い表現は「高コンテクスト」(共有される前提や背景知識が必要)であり、外部の者には理解しにくいとされる。しかし、「雪」という誰もが知る自然現象が対象である「それスノ」は、極めて低コンテクストですらある。日本に住み、雪を知っていれば、老若男女、誰でもその瞬間の感情を想像できる。この「参入障壁の低さ」と「感情の普遍性」が、爆発的な広がりを可能にした土壌なのである。
第3章: SNSとメディアにおける「それスノ」現象の拡大
「それスノ」は、単なる個人のつぶやきの域を超え、大きなうねりとなってメディアや商業空間にもその影響を及ぼし始めた。
・ハッシュタグ (#それスノ) の隆盛
TwitterやInstagramでは、雪の季節になると #それスノ ハッシュタグがトレンド入りするのが恒例行事となった。これは、日本全国、さらには海外在住の日本人からも、その土地その土地の雪景色が一挙に集められるプラットフォームを提供する。北海道の深雪から、九州の珍しい積雪、はたまたパリやニューヨークの雪景色まで、一個のハッシュタグで巡る世界の雪見ツアーが可能になる。これにより、現象は「個人の感動」から「集合知的な風景コレクション」へと変貌を遂げた。
・伝統メディアや天気予報での採用
その認知度の高さから、民放のテレビ番組やニュースサイトの天気コーナーでも、「それスノ」という表現が使われるようになった。気象予報士が「さて、明日の朝は『#それスノ』なところがあるかもしれませんね」などと、視聴者との親近感を醸成するためのツールとして利用するのである。これにより、ネット発の表現が完全に主流の文化に取り込まれたことが確認できる。
・自治体のプロモーションへの応用
観光地、特に雪国の自治体は、この現象を巧みにプロモーションに利用している。公式Twitterアカウントで美しい雪景色の写真とともに「#それスノ」と投稿し、観光客を呼び込むのである。例えば、新潟県や長野県、東北地方の自治体は、都会の住民にとっての「非日常」を自らの「日常」として発信することで、その価値を最大化させることに成功している。
第4章: 最新の動向と進化形 ― 「それスノ」のその先へ
「それスノ」現象は静態的ではなく、常に進化し、派生し続けている。ここでは、最新の動向や関連する派生現象を紹介する。
1. 季節を超えた「それ○○」への派生
「それスノ」の成功は、他の事象に対しても同様の表現形式を生み出す土壌となった。つまり、「それ○○」というフォーマットの誕生である。
- #それ虹:雨上がりに現れた虹を発見した時の感動を共有。
- #それ月:特に美しい満月や月食を目撃した時の報告。
- #それ雷:不気味ながらも迫力のある雷光を捉えた瞬間。
- #それ桜:春先、開花した桜を発見した喜び。
これらは全て、「それスノ」が確立した「非日常的な自然現象の瞬間的・視覚的共有」というジャンルをさらに細分化し、一年を通じて共感の循環を生み出している。
2. 企業のマーケティングへの本格参入
最新の動向として、企業のマーケティング戦略への深い統合が挙げられる。単なるハッシュタグの使用ではなく、現象の本質を理解した上での巧みな campaigns が展開されている。
- カメラメーカー・スマホメーカー:「#それスノ」の瞬間を最高の画質で捉えよう、という訴求。夜景モードや手ぶれ補正機能のアピールに最適な場となっている。
- アパレル・アウトドアブランド:美しい雪景色を背景にした自社のジャケットやブーツを紹介。「機能性と美観の両立」を自然な形で伝えられる。
- 食品・飲料メーカー:温かいコーヒーやココア、あるいは鍋の具材など、雪景色と共に楽しみたい商品を、「#それスノ」の写真と絡めて提案する。
これらは、従来の硬直した広告ではなく、ユーザー生成コンテンツ(UGC)の文脈に自社商品を溶け込ませる、現代的なマーケティングの好例となっている。
3. AI画像生成と「創造」としてのそれスノ
2023年から2024年にかけて最も顕著な最新動向は、AI画像生成サービスとの融合である。Stable DiffusionやMidjourneyといったツールの普及により、ユーザーは現実に雪が降らなくても、「それスノ」のイメージを創造できるようになった。
- ファンタジー風景の創造:「富士山と侍と雪」といった現実にはない壮大な雪景色を生成し、「#それスノ #AI」などとタグ付けて投稿する。
- ノスタルジアの喚起:「昭和のレトロな街並みに雪が降る」といった懐かしい風景を再構築する。
- キャラクターとコラボ:アニメやゲームのキャラクターを雪景色に登場させたイラストを生成する。
これにより、「それスノ」は単なる「発見と報告」の領域から、「創造と表現」の領域へと大きくそのステージを広げた。雪はもはや、待つものではなく、創り出すものになったのである。
第5章: 批判的視点と今後の展望
どんな文化現象にも影の部分はある。「それスノ」についても、いくつかの批判的・問題点が指摘されている。
- 交通麻痺や災害の軽視:美しい雪景色の裏側で、通勤や物流が麻痺し、高齢者や災害弱者にとっては命の危険に関わることもある。そうした現実から目を背け、唯美主義的に雪を礼賛する風潮への批判。
- 「撮って投稿」の強迫観念:眼前の風景を純粋に体験するよりも、まずはSNSに上げることを最優先する現代の風潮を象徴する一面もある。体験の二次化、デジタル化が進みすぎているという指摘である。
しかしながら、これらの批判は現象そのものを否定するものではなく、その享受の仕方に対する注意喚起と言える。今後、「それスノ」現象はさらに進化を続けるだろう。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術が発展すれば、静止画や動画を超えた没入型の「それスノ」体験が共有される日が来るかもしれない。
結論: ささやかな共感が紡ぐ、現代のデジタル俳句
「それスノ」は、一過性のネットスラングでは終わらない。それは、デジタル時代における日本の「間」の文化の新しい形である。
それは、俳句が五・七・五の十七音で季節の情感や人生の機微を詠み込むように、わずか三文字で一瞬の自然の驚異と、それに対する人間の心の動きを詠み込んでいる。そして、インターネットという俳句の「吟行」場を、日本全国、いや世界へと拡張した。
寒い朝、カーテンを開けて「それスノ」と呟く。その同じ瞬間に、何百人、何千人もの人々が同じ感動を共有している。たとえ物理的には孤独でも、デジタル空間では無数の共感に囲まれている。その実感こそが、この現象の最大の価値である。
雪はいつか解ける。トレンドのタグもいつかは過去のものになるだろう。しかし、非日常の美しさを発見し、それを他者と分かち合いたいという人間の根源的な欲求は、これからも形を変えながら、次の「それスノ」を生み出し続けていくに違いない
https://www.tbs.co.jp/sore_snowman